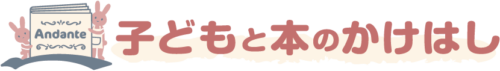戦後80年の8月6日 アーサー・ビナードさんの講演
教員免許と司書・司書教諭の資格を持つ【絵本専門士】である【現役 学校司書】が発信するお役立ちサイト。🔰さんからベテランさんまで、学校図書館に携わる方が、明日から使える情報とダウンロードできる資料が満載✨

『さがしています』(写真/岡倉禎志 出版/童心社 2012)でおなじみのアーサー・ビナードさんの講演会が、親江会(東京都江戸川区 原爆被害者の会)主催で開催されました。
主催してくださった親江会の方々、登壇してくださった方々に感謝と敬意を込めて、発信させていただきます。
午前中は、講演と紙芝居を演じてくださり、午後は講演と『さがしています』を朗読してくださいました。
【絵本専門士のおすすめ】
『さがしています』
著/アーサー・ビナード 写真/岡倉禎志
出版/童心社 2012
広島の原爆で命を落とした方々の遺品たちが、今もなお、持ち主の声・ぬくもりを探していることを写真とともに綴った写真絵本。講談社出版文化賞絵本賞などの賞を受賞。
紙芝居は時代の断絶がないメディア
ビナードさんは、アメリカにはない、日本の「紙芝居」に魅せられたそうです。
アメリカの大学で日本語を学んだいきさつ、23歳で来日した当時のこと、図書館で紙芝居に巡り合ったこと、など現在までをユーモラスに語ってくださいました。
温かい偶然の巡り合わせが積み重なって、現在のビナードさんがある、ということがよく分かりました。
NHKドラマ「船を編む」で覚えた言葉「セレンディピティ」を彷彿させるエピソードに胸を打たれました。
紙芝居を演ずる時に入れる木の箱のようなものを「舞台」と言います。
ビナードさんは「この箱はなんだろう?」と思っていたら、素晴らしい劇場が始まり、大変感動したとおっしゃっていました。
時代とともに記録媒体は変化し、映し出せる機械も変化してきました。
しかし
「紙芝居は時代の断絶がない、待ち受け時間も、コードも電気もいらない素晴らしいメディア」
とおっしゃっていました。
今回はまず『ラクカサンブタイ』(落下傘部隊)という、戦時中、それも終戦の前年1944年11月に発行されたという紙芝居を演じてくださいました。
日本昔話の「金太郎」を模して、部隊長がキンタロウで登場人物が動物でした。
落下傘で適地へ降り立ち、堀の深い顔立ちの敵を次々に倒し・・・強いニッポンを強調する物語でした。
前の方に座って聞き入っていた小学生のお子さんは「逆じゃない?」とするどいつぶやきが耳に残っています。
紙芝居制作の7年
そのアメリカにはない、日本のメディアである紙芝居を「いつか作ってみたい」と思ったそうです。
7年間、「ピカの体験者に耳をかたむけつづけた。いのちの源であるサイボウ(細胞)にも耳をすまして形になった」という『ちっちゃい こえ』(脚本/アーサー・ビナード 絵/丸木俊・丸木位里 出版/童心社 2019)を演じてくださいました。
絵は丸木俊さん・丸木位里さんの壮大な「原爆の図」から部分的に選ばれ、構成されているそうです。
目をそむけたくなるような、深く心の入り込んでくる「原爆の図」にどんな風に向き合い、どんな対話をしながら作成されたのでしょうか。想像を絶します。
ネコに導かれて展開するストーリーの「命の叫び」「サイボウの嘆き」「平和への祈り」に圧倒されました。
【絵本専門士のおすすめ】
『ちっちゃい こえ』
(脚本/アーサー・ビナード 絵/丸木俊・丸木位里 出版/童心社 2019)
ネコがナビゲーターとなって展開していく物語。丸木俊さん・丸木位里さんの偉業「原爆の図」から絵を切り取り、構成されている。小さな命の「ちっちゃいこえ」は平和を願ってこだまします。
第58回五山賞特別賞 受賞作品
参考になる記事
「原爆の図」を7年がかりで紙芝居に。詩人アーサー・ビナードさんが伝えたかった「ちっちゃい こえ」とは?▶
2019年 生協の宅配パルシステムさんのビナードさんへのインタービューの記事です。
ビナードさんのおすすめの詩集、2冊
午後はまた、軽やかで優しく、楽しいトーンでビナードさんの講演が始まりました。
だからこそ、秘めた熱い思いは、随所に響き、胸に刺さります。
詩人のビナードさんのおすすめの詩集を紹介してくださいました。
まず1冊目は『原爆詩集』(作/峠三吉 出版/岩波書店 2016初版)。
峠三吉は1917-1953(享年36歳)、ビナードさん曰はく「平和を体験していない」とのこと。
有名な「序」(「ちちをかえせ ははをかえせ・・・」)を含む詩と、「その日」「二日め」と峠さんが目にして、耳に残っている当時の様子を記録として残し、「あとがき」では命を削って、未来に平和のバトンを渡したい一心で出版されたと想像できます。
「あとがき」に記された日付は、1952年5月10日です。(1953年没)
ビナードさんの『さがしています』でも選んだ「人影の石」(住友銀行広島支店の入口階段の石。銀行の開店を待つ人が座っていた時に被爆したらしく、人の姿はないが、階段には影のように黒く残っている。現在は広島平和記念資料館に移設。)が、詩中にうたわれています。
絵本専門士おすすめの詩集
『原爆詩集』
詩/峠三吉 出版/岩波書店 2016
(アマゾンでは品切れ中につき、他の出版物を紹介します)
原爆が落とされた瞬間のこと、命を奪われた人々、また苦しみ続けた人々が克明に描かれています。不安定な現代だからこそ刮目しないといけない現実がそこにあります。
1951年ベルリンの全世界青少年学生平和祭に、日本代表作品の一つとして送られ、世界的な反響を与えた。 広島平和記念資料館HPより
2冊目は、「なかなか手に入らない」と注釈を入れながら、『原子野に生きる』(詩/福田須磨子 編/長崎証言の会 出版/汐文社1989)です。
中でも「ひとりごと」が代表的な詩だそうです。
極限状況の体験を表現する詩や文学を読むことは、被爆者のおかれた心理の理解を深める。被爆者による被爆遺構めぐりのなかでも引用されることがある、福田須磨子さんの詩である/長崎大学 核兵器廃絶研究センター サイト
引用元でありますサイトで読むことができます。
絵本専門士も読んでみたい詩集
『原子野に生きる』
詩/福田須磨子 編/長崎証言の会 出版/汐文社1989
強い視線で長崎で戦後を見つめた詩人が、心の叫びと祈りを強い言葉で語っています。後世に残したい1冊。
『さがしています』
ビナードさんが自ら『さがしています』を朗読してくださいました。
広島平和記念資料館の近くに移り住んだビナードさんは、幾度となく通い、遺品の数々と対面して、作成された写真絵本です。
「声なき相手にずっと耳をすましていた。そのものたちにひそむ物語を、通訳者として言葉で伝えたいと思うようになった。資料館の地下収蔵庫にある約2万1千点の中から、14点の収蔵品を選び、本書に登場してもらった。そのカタリベたちが、今生きているわたしたちに何を手わたすのかーひとりひとりの「さがす物語」が始まる。」(省略部分あります/童心社 『さがしています』注文書より)
その「カタリベ」とは、軍手・お弁当箱などの日用品、愛用品たち。
「カタリベ」たちが被爆する前のありのままの日常と、被爆の瞬間、朝8時15分を語ります。
被爆前と被爆後は「ピカアアアアアア」という言葉で表しています。
「カタリベ」たちは被爆した持ち主の帰りを待っています。今もさがしています。
小学校5年生の光村国語教科書に掲載されている『たずねびと』で主人公が広島平和記念資料館で見たものと重なります。
すべての人に送りたい絵本ですが、小学校5年生に是非とも読み聞かせしたい写真絵本です。
【絵本専門士のおすすめ】
『さがしています』
著/アーサー・ビナード 写真/岡倉禎志
出版/童心社 2012
広島の原爆で命を落とした方々の遺品たちが、今もなお、持ち主の声・ぬくもりを探していることを写真とともに綴った写真絵本。
講談社出版文化賞絵本賞などの賞を受賞。
笑いと感動、胸がいっぱいの1日
8月は、子どもの頃からずっと「平和について考える季節」。
「原爆」「戦争」というと重い気持ちになります。
ビナードさんの作品を読んで、ビナードさんご自身に大変興味がありました。
講演を拝聴する前には、いくらかの緊張がありました。
ビナードさんはアメリカ人なので、アメリカ人としての視点で戦争・原爆の捉えてお話しなさるのか。
日本人との温度差はないのか。
自分は講演後も同じ気持ちで『さがしています』を読むことができるのか。
または、アメリカ人のビナードさんが、原爆のことを掘り下げて見つめているのに、「日本人なのにそんなことも知らないの?」と不勉強を軽蔑されるのか?
紙芝居はどのように演じられるのか。
感情を露わにして、訴えるように演じるのか?
身構えていましたが、全くの杞憂で、ビナードさんのお人柄にすっかり魅了された1日でした。
流暢な日本語で「私はこう見えてアメリカ人です」と、最初に笑いを提供して場をなごませてくださいました。
そして、紙芝居を演ずる時に、マイクを手に持つことができないので、ワイヤーハンガーの三角の輪に頭を入れて、物干し竿に掛ける湾曲した部分にマイクを入れて両手を空ける時など、随所にユーモアあふれる話術で、重いテーマでも苦しい思いをすることなく、穏やかに平和を願う気持ちになりました。
紙芝居は、押し付ける感じでもなく、内容とストーリーをきちんと伝えてくださり、ストレートに心に届きました。
本企画では、広島カープ元監督でもあられた山本浩二さんもご登壇されお話しされました。
「広島県民にはスポーツで喜んでもらいたい気持ちはいつもあった」「風化させないことが大切」というお言葉が印象的でした。
また「諸外国とは文化・スポーツなどで交流することで理解が深まり、仲良くなれば、平和につながる」というお話もでてきました。
被爆二世の古今亭菊太郎さんの新作落語「母のお守り」も心が温まりました。
お母さんが子どもにお守りを持たせる時に「しっかりした組みひもがついているから落ちないよ」という意味が最後につながり、大変驚き、落語の素晴らしさと奥深さを体感しました。
古今亭菊太郎さんの優しい声とまなざしに癒され、落語に笑い、オチで目を丸くし、心を射抜かれた20分でした。
今、様々なサイトで「平和を考える絵本」が紹介されています。
戦後80年、これからも【戦後】が永遠に続くますように。