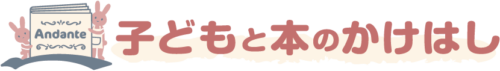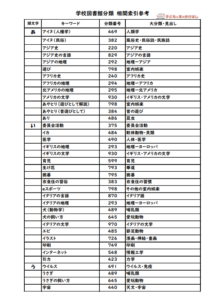正しい排架は子どもの未来のため|配属先の排架を直す方法
「私が困ったことは、みんなには困らせたくない!」教員免許、司書・司書教諭の資格を持つ現役学校司書が発信する「お役立ちサイト」✨初心者さんからベテラン学校司書さんにも役立つ情報やダウンロードできる資料が満載!

学校に配属されて、まず見て欲しい、やって欲しいのは【排架】本を所定の場所に並べることです。

配属された学校図書館の排架が間違ってて・・・
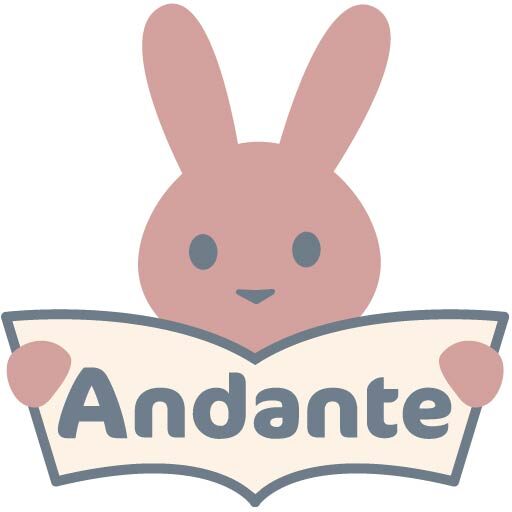
そうでうね。学校司書が初めて入った学校は、まず排架の見直しを。
排架を直す勇気
前に学校司書さんがいた学校図書館は(たぶん)正しく排架されていると思います。
しかし初めて学校司書が入った学校の学校図書館は、先生方やボランティアさんが「よかれ」と思って排架してくれた場合があります。

排架が間違ってるけど、もう子どもたちもこの排架に慣れてるし、せっかく並べてくれた人に悪くて、言い出せない・・・
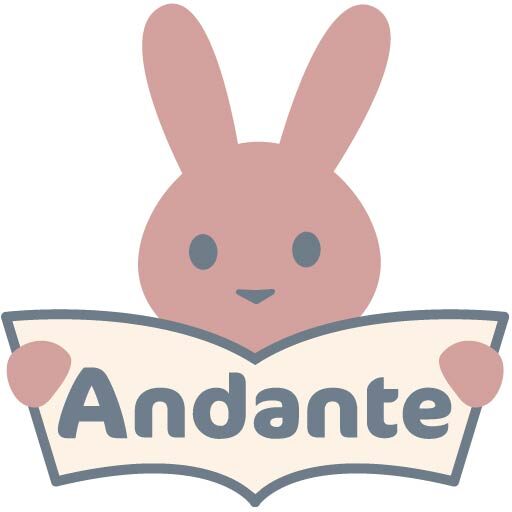
悩みますよね💦
でも、子どもたちの未来のために、排架を直しましょう!
子どもは排架を直しても、対応する力があります。
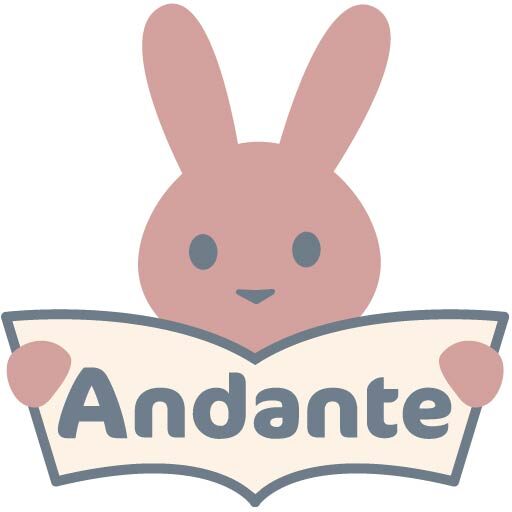
子どもたちを信じて!
排架は左から右へ
排架は【左から右に】本を置きます。
もし、反対まわりになっていたら、大変ですがやり直しましょう。
基本は大切です。
教科書と合わなくなってしまいます。
一人でやることは難しいです。
学校(管理職)に相談をして、先生方に手伝ってもらうか、ボランティアさんを募りましょう。
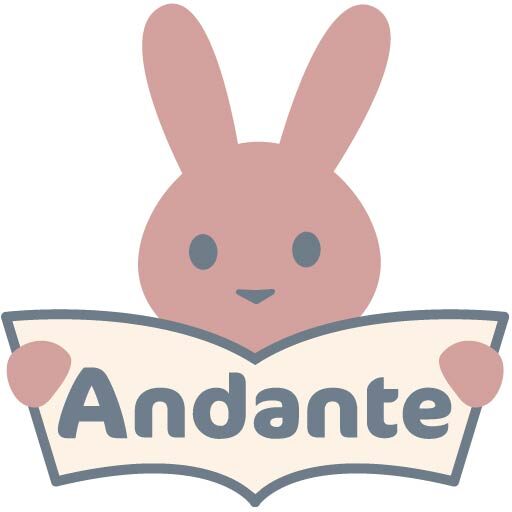
勇気を出して!
「図書館のプロ」が入ったのだから、大改造が必要です!
排架は案外うまくいく!
左から右に本を置くことができれば、0類は図書館の中のどこから始まっても大丈夫です。
「分かりやすい」から「図書館の端から順に並べたい」気持ちはよく分かりますが、最適な棚割りを優先して考えます。
排架の留意点
- 各分類の量を見る(本の厚みが違うので、冊数ではなく、目で見ましょう)
- 本の高さを見る(9類の物語はあまり棚1段の高さは必要ありません。棚板が可動の場合は、大きい本を入れることができるので、生かしましょう)
- 低学年が手に取るのは4類と7類が多い(手に取りやすい低めの書架が好ましいです。3類に低めの書架はもったいない)
- 百科事典や図鑑は子どもにとってはとても重いので、高い棚は危険です
- 絵本コーナーを作りましょう(絨毯など、上履きを脱いでくつろげるスペースがあるとよい)
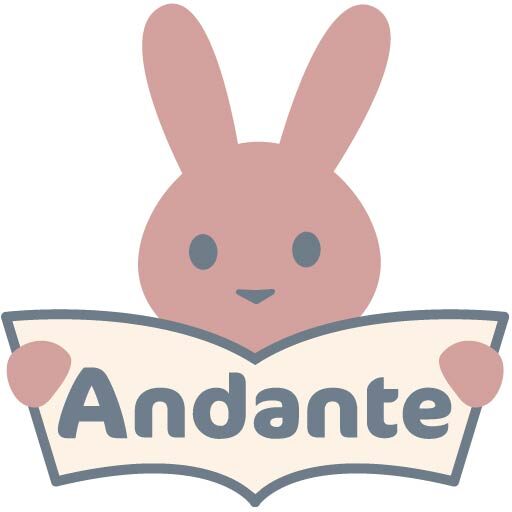
私は数回、図書館の排架を決めました。
「ちゃんと入るかな?」と悩みましたが、元々入っていたものだし、入ります。
たくさん考えた後は、もうこれ以上の排架はないと思っています。
これが【正解】!
各分類の本の量
多くの小学校の学校図書館を見て、各分類の本の量「だいたいこんな感じ」をお知らせします。
学校により、差があるので「おおよそ」です。
ご参考までに・・・
(数字は一般的な書架の数:高さ180cm 幅90cm )
| 0類 | 1.5(各分類の図鑑も入れ、百科事典は2セットの場合) |
| 1類 | 0.5 |
| 2類 | 2(伝記が多ければ2.5) |
| 3類 | 2 |
| 4類 | 4.5 |
| 5類 | 1(SDGsを5類にすると1.5) |
| 6類 | 0.7 |
| 7類 | 1.5 |
| 8類 | 1 |
| 9類 | 10 |
あふれてしまった本は、隣の分類に「間借り」したり、「大きすぎて入らなかった本たち」の棚に移したり、どこかに収まります。
余裕があれば、高さ180cmの一番上段は使わないとよいです。(子どもが届かない)
分類のサインを置いたり、イメージ画を置いたりして活用しましょう。
まとめ
いつかはやらなくてはいけない「正しい排架」。
それが「今」ではだめですか?
学校司書さんには、体にも心にも「負担」になりますが、【子どもの未来のために】できるとよいです。
「言い出せない」・・・よく分かります。
でも「図書館のプロ」が入ったのだから、そこは理解してもらえます。
「教科書に載っているので」と管理職に伝えましょう。
後になって「やってよかった」と皆さんが思ってもらえると信じています。
役に立つ記事
書架の整理▶ 「日本十進分類法」で並べることが解説されています。サインもダウンロードできます。