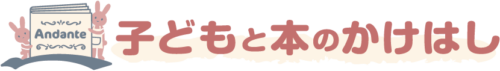教員免許、司書教諭、司書資格を持つ絵本専門士である、現役学校司書がお届けする、学校図書館のためにお役立ちサイト。🔰さんからベテランさんまで、すぐに使える情報とダウンロードできる資料も満載!

アニマシオンってなに?
本を読み聞かせしたり、紹介したりして、読書推進を行っていると思います。
もうひとつ、子どもが「読みたい!」「本って楽しい!」と思える【読書ゲーム】が「アニマシオン」です。
子どもの力を引き出します。
アニマシオンとは
- マリア・モンセラット・サルト(1919年、スペイン生まれ)により考案
- 読書教育方法
- 代表作品『読書へのアニマシオン 75の作戦』
- ランテ語で「魂の活性化」という意味
- アニマシオンをする人(仲介者)を「アニマドール」と呼ぶ
この頃から、「子どもの読書習慣」「社会一般における活字離れ」に頭を抱えていたようです。
「予測困難な現代」だからこそ、より読書の重要性は高まっているでしょう。
難しくない!あなたもできる!アニマシオン
アニマシオンの方法はM・M・サルトも75の作戦を提案しています。
選ぶ本・絵本、対象者、対象人数や年齢によって、また、アニマドールによって、様々に変化するのが、また楽しいところです。
本や絵本を読んでいると「あ、これアニマシオンにすると楽しそう!」と思えるようになります。
1クラスが、図書館や教室で行えるのもを想定しました。
「少人数が望ましい」「中高生向き」「全員が同じ本を事前に読んでくる」という制限がないものを選びました。
さっそくやってみましょう。
目次
- ダウトをさがせ(小道具などの準備は必要なくお手軽)
- これ、だれのもの?
- 前かな、後ろかな?
- だれが言ったかな?
- これ、だれのこと?
- 谷川俊太郎さんに挑戦!
- 何をたべたんだっけ?
- 地図を作ってみよう
- 〇年〇組おいしいレストラン
ゲームの名前は、M・M・サルト氏がつけたものと、筆者が解釈して実践し、名付けたものが混在しています
1.ダウトをさがせ
アニマシオンの代表、🔰向きで、子どもも大好きです。
いつでも、どこでも、読み聞かせの練習以外、事前の準備もなくできます。
読み聞かせをしている時に、間違えた言葉に気が付いたら、子どもが「ダウト」と言って、正しい言葉を子どもに答えさせるゲームです。
やり方
- 絵本の読み聞かせの前に言っておきます→「これからこの本を読みます。よく聞いて、よく見て、よく覚えてください。
- 絵本の読み聞かせ
- ゲームの説明→「もう1度、絵本を読みます。途中で間違えてしまうかもしれません。気が付いたら「ダウト」と言ってくださいね。だるまさんのダ、牛さんのウ、とびらのト、でダウト、ね。その後、「正しいのは何ですか」と尋ねたら、正しい言葉を教えてください。」
- 2度目、同じ本を間違えながら読み聞かせ
<注意事項>
「もし、お友だちがダウトでないところで「ダウト」と言ってしまっても、笑わないこと。勇気を出して、一人で「ダウト」と言った勇気に心の中で拍手をしてください。」と言っておくと楽しい雰囲気で終わります。
使える絵本
〇『みんながおしえてくれました』 作/五味太郎 出版/絵本館 1983年
たくさんの動物が「走り方」や「土の中の秘密」などを教えてくれます。動物を「大谷選手」や「校長先生」など、「ちがうよー」と笑えるものを考えるのも楽しいです
〇『11ぴきのねこ』作/馬場のぼる 出版/こぐま社 1967年
「大きな海」を「小さな池」、難しい言葉「ねんねこさっしゃれ」を「校歌」と言い間違えて、正しい言葉を考えさせるのも楽しいです
2.これ、だれのもの?
絵本に登場する動物や人の持ち物や部屋にあったものを、だれの持ち物だったか当てるクイズです。
やり方
<準備>
登場人物や動物と持ち物を、絵または文字で書いたカード(子どもたち全員に見えるくらいの大きさ)
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、よく見て、よく覚えてください。特に洋服や身に付けているもの、部屋の中に注意してくださいね」
- 絵本の読み聞かせ
- 黒板(ホワイトボード)に登場人物を貼る
- 持ち物をひとつ、ひとつ見せて、誰のものか答えてもらう
後ろの方の子どもが見えにくいことがあるので、テキストに出てきたものや、想像すると答えることができるものなど、工夫しましょう
使える絵本
〇『ともだちや』 文/内田麟太郎 絵/降矢なな 出版/偕成社 1998年
多くの動物の部屋が出てきます。実際に絵本の絵が見えなくても「でんでんだいこ」は赤ちゃんがいた鳥の巣かな、と推理できます。最後、車をオオカミがキツネにあげます。赤い車と青い車が登場し、「今はだれのものでしょう」とひねった問題も楽しいです
〇『てぶくろ』 絵/エウゲーニー・M・ラチョフ 訳/内田莉莎子 出版/福音館書店 1965年
ウクライナの民話です。各階級の服装をしている動物たちが、次々に落ちていた人間の手袋に入っていきます。手袋の中には、階級の違う人が一緒に入っている、という深い意味も感じられる絵本です。
3.前かな、後ろかな
絵本の物語の順番に並び替えるゲームです。
やり方
<準備>
登場人物や出来事をカードに書いておく(子ども全員に見える大きさ)
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、よく見て、よく覚えてくださいね。」
- 絵本を読み聞かせる
- カードを裏返して1枚ずつ配る
- 最初の人だけカードを頭の上に掲げてもらう
- 2番目の人がカードを掲げて、最初の人のカードより、前か後かを考えて、前だったら最初の人の右側に、後だったら、最初の人の左側に立つ
- 3番目も同様に順を考えて、人の間に入れてもらったり、順に並んだりする
カードが多いと楽しいですが、時間がかかります。
人数分、準備できない場合は代表者が並び、皆で考えるのも楽しいです。
その場合、カードを持っている人が、自分は何のカードなのか見ないで、順に並んだ後に何のカードだったか当てる、というおまけをつけてもよいでしょう。
使える絵本
〇『これはのみのぴこ』 文/谷川俊太郎 絵/和田誠 出版/サンリード 1979年
人気の本です。最後にみんなで答え合わせをするのが楽しいです
〇『王さまと九人のきょうだい』 訳/君島久子 訳/赤羽末吉 出版/岩波書店 1979年
同じく人気の本です。読み聞かせをするのにも時間がかかるボリュームのある絵本です。ゲームは別の日にしてもよいでしょう。記憶があいまいになり、また違う楽しみかたもあるかもしれません。
4.だれが言ったかな?
登場人物の言った言葉で、誰が言った言葉なのかを当てるクイズです。
やり方
<準備>
登場人物と言った言葉をカードにします(子ども全員が読める大きさで)
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、よく覚えてくださいね。」
- 絵本を読み聞かせる
- 黒板(ホワイトボード)に登場人物を貼る
- セリフのカードを見せて、誰が言ったことなのかを当てる
長いセリフでもよいし、単語だけでもよいでしょう。
使える絵本
〇『せかいいちおおきなうち』 作/レオ=レオーニ 訳/谷川俊太郎 出版/好学社 1969年
大きくなりすぎたかたつむりを見て、動物たちが好きなことを言います。誰が何と言ったか覚えているかな?
〇『うろおぼえ一家のおかいもの』 作/出口かずみ 出版/理論社 2021年
うろおぼえ一家がお母さんに頼まれたものを買いに行きますが、何だったか思い出せません。「白い」「重い」など特徴は覚えています。道で出会った動物たちに「石じゃない?」など推理してくれます。誰が推理したものか当ててみましょう。
5.これ、だれのこと?
絵本の登場人物のセリフから性格を読み取ってみましょう。
どんな人(動物)なんでしょうかね?
やり方
<準備>
登場人物と性格や性質を言葉にしたカードにします(子ども全員が読める大きさで)
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、どんな人なんだろうと想像してみてください」
- 絵本を読み聞かせる
- 黒板(ホワイトボード)に登場人物を貼る
- 性格や性質のカードが誰のことなのかを考える
絵本を読み聞かせしていると「ひどい」や「かわいそう」など、心の声が聞こえてくることがあります。
それをすくい取り、自分がどのように見ているのか、感じているのかが分かります。
読書感想文などにもつながる深い読みができます。
使える絵本
〇『王さまライオンのケーキ はんぶんのはんぶん ばいのばいの おはなし』 作/マシュー・マケリゴット 訳/野口絵美 出版/徳間書店 2020年
傲慢で自分勝手な動物たちが王さまライオンに招かれます。正直者のアリは大変恥ずかしい思いをさせられます。読み聞かせの後は、必ず取り合いになる、とても心の響く物語りなので、ゲームにするものはばかれる気もしますが、絵本をおさらいする意味では、有効的だと思います。
〇『かにむかし』 文/木下順二 絵/清水昆 出版/岩波書店 1976年
さるかに合戦の昔話です。登場人物が印象的で、想像しながら当てると楽しいです
6.谷川俊太郎さんに挑戦!
絵本に副題をつけるゲームです。
スイミーをはじめてとするレオ=レオーニさんの作品には、副題がついています。
原作にはついていません。
例えばスイミーは「ちいさなかしこいさかなのはなし」となっています。
絵本や科学絵本、教科書の物語、読みものの本などの作品に「副題をつけてみる」活動をします。
子どもにカードに書かせて、投票してみても楽しいです。
「要約」や「読書感想文」の練習にもなります。
何を食べたんだっけ?
食べ物が出る絵本があります。
読んでいるとおなかがすいてきます。
何を食べたのか考えると、ますますおなかがすくでしょう。
やり方
<準備>
食べた食べ物と食べていない食べ物(ダミー)をカードにします(子ども全員が見える大きさで)
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、よく覚えてくださいね」
- 絵本を読み聞かせる
- 黒板(ホワイトボード)に食べ物を貼る
- どれを食べたのか考える
ダミーがポイントです。
似ている食べ物にすると難しくなって楽しいです。
使える絵本
〇『なにをたべたかわかる?』 作・絵/長新太 出版/絵本館 2003年
ネコが釣った魚を担いで歩いていると、色々な動物が後ろからやってきて、こともあろうに担がれた魚がその動物たちを食べてしまいます。みるみる大きく重くなる魚。いったい何を食べたのか、カードから選んでみましょう
〇『はらぺこあおむし』 作/エリック・カール 訳/森ひさし 出版/偕成社 1976年
大人気の絵本で、すっかり覚えている子どもも多いでしょう。でも数までは覚えているでしょうか?スモモだったかな、モモだったか。最後にたくさんの食べ物が並んでいますが、ニンジンは入っていたかな?
地図を作ってみよう
絵本を読んで、地図を書いてみよう。
『エルマーのぼうけん』文/ルース・スタイルス・ガネット 絵/ルース・クリスマン・ガネット 訳/渡辺茂男 出版/福音館書店 1963年 や『のはらうた』詩/工藤尚子 に見返しに地図が描かれていて、ワクワクします。
やり方
<準備>
家やお店のカードを班の数だけ作る
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、よく覚えて、想像してくださいね」
- 絵本を読み聞かせる
- 白い紙(模造紙の半分が最適)と建物を班に配る
- 地図を書いてみる
使える絵本
〇『ぶたぶたくんのおかいもの』 作・絵/土方久功 出版/福音館書店 1985年
初めてこの絵本を読んだ時に「あれ?」と思った人は多いと思います。ぶたぶたくんは野菜やおかしを買った後、引き返そうとすると友だちに「まっすぐ行った方が、家に近いよ」と言われます。「どういうこと?」を地図にしてみましょう。班で話し合って、「ぐるっと」や「まるい」というキーワードが出るとGOOD✨
〇年〇組おいしいレストラン
苦手な食べ物を描いて、美味しそうな名前をつけます。
楽しくお絵描きをする活動です。
先生も「私も描きたい」と参加を希望する方もいらっしゃいます。
やり方
<準備>
子どもに色鉛筆を持ってきてもらう
白い紙を用意する
<やり方>
- ゲームの説明→「これから絵本を読みます。よく聞いて、想像してくださいね」
- 絵本を読み聞かせる
- 白い紙を配る
- 苦手な食べ物の絵を描いて、好きな名前をつける
- 回収し、大きな模造紙に張り付ける
使える絵本
〇『ぜったい たべないからね』 作・絵/ローレン・チャイルド 訳/木坂涼 出版/フレーベル館 2016年
苦手な食べ物が多い妹に、お兄ちゃんが美味しそうな名前をつけて、食べたくなるようなエピソードを言ったら、食べられるようになりました。お豆は「あめだま みどり」で宇宙からきたものだとか。みんなも考えてみよう!
子どもたちが描く前に、アニマドールが例を作っておくとよいでしょう。
しいたけの絵を描いて「ぐんにゃり かさ」やピーマンの絵を描いて「カラカラおみくじ」など。
「てんとうむしが傘にして、しいたけへの感謝の気持ちがしみているから、噛むとじゅわっと液体がでる」や「ピーマンをかじって、中におみくじが入っていたらアタリ」などエピソードも加えましょう。
人がやったものを見ると「やりたい!」気持ちがアップします。
苦手なものでなくても、みんなに食べてもらいたいものでも何でもOKです。
「好き嫌いがある」ということはいけないこと、と思っている子どももいます。
「好きなものでいいんだよ。みんなが喜びそうな名前をつけてね」と声をかけます。
まとめ
初めての方にもできそうなものを集めてみました。
アニマシオンをすると、子どもたちも本や絵本に親しみを持てます。
読み物でクイズを出すと、読んだことのない子どもが「読むと答えられるんだ」と前向きな気持ちで本を読むことができます。
準備するものも、1度作ると何年も使うことができます。
「3年生にはコレ」と決めておけば、毎年準備する必要はありません。
「今年は低学年はコレ」となると、来年はまた考えるところから始めなくてはいけないので、学年で決めることをおすすめします。